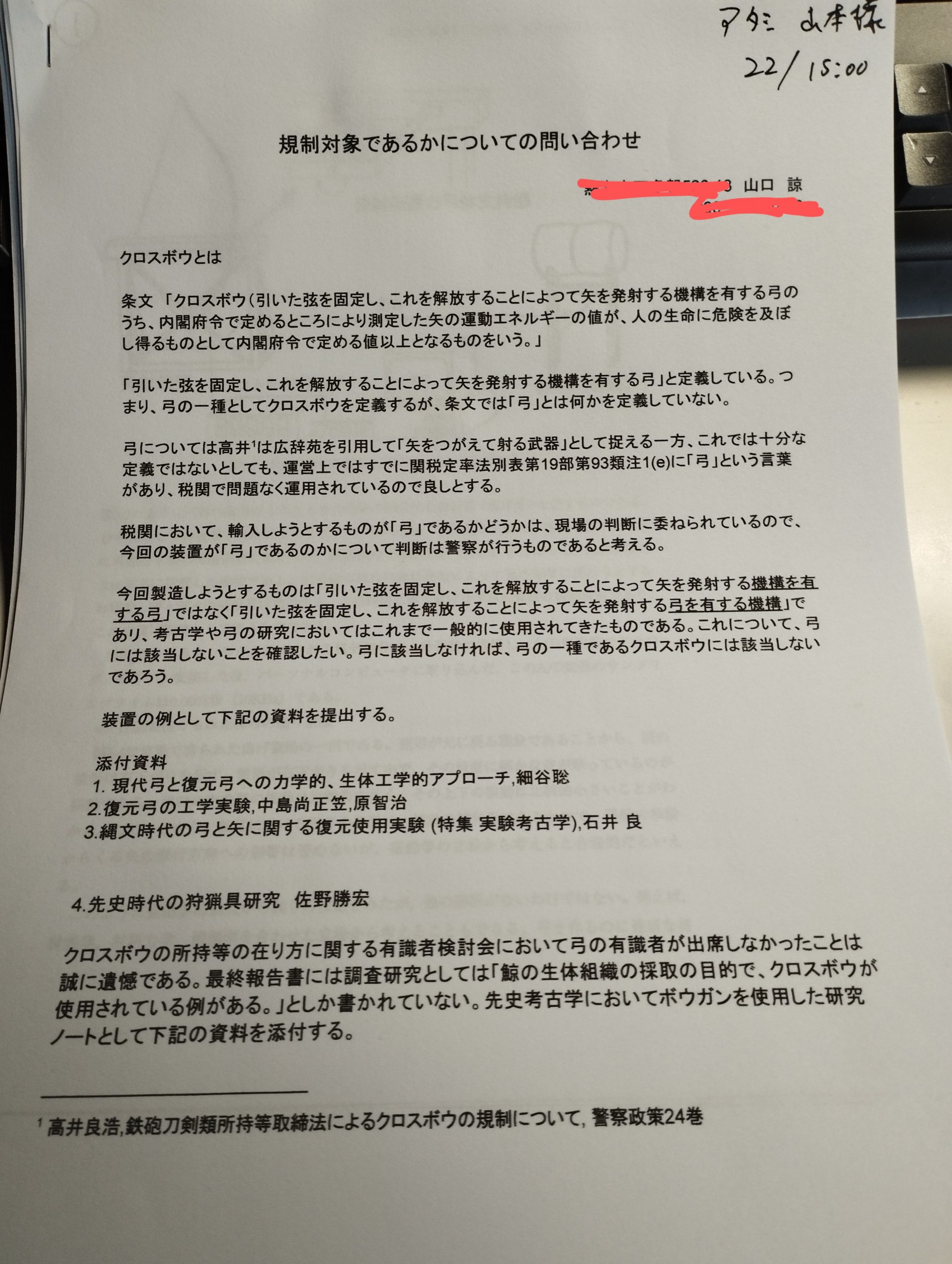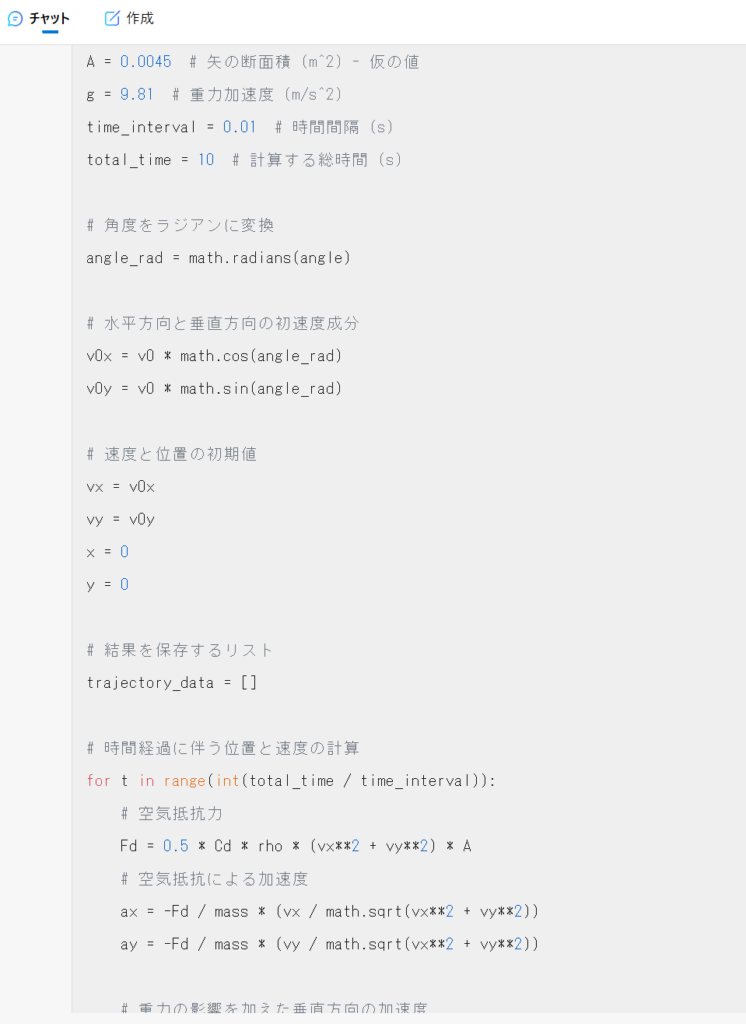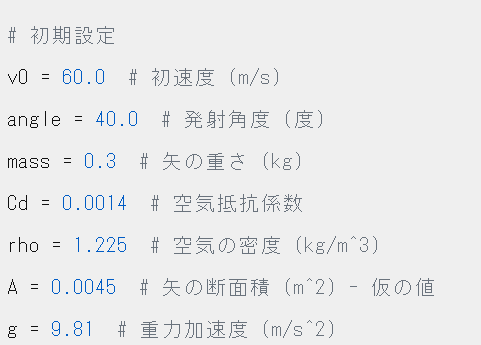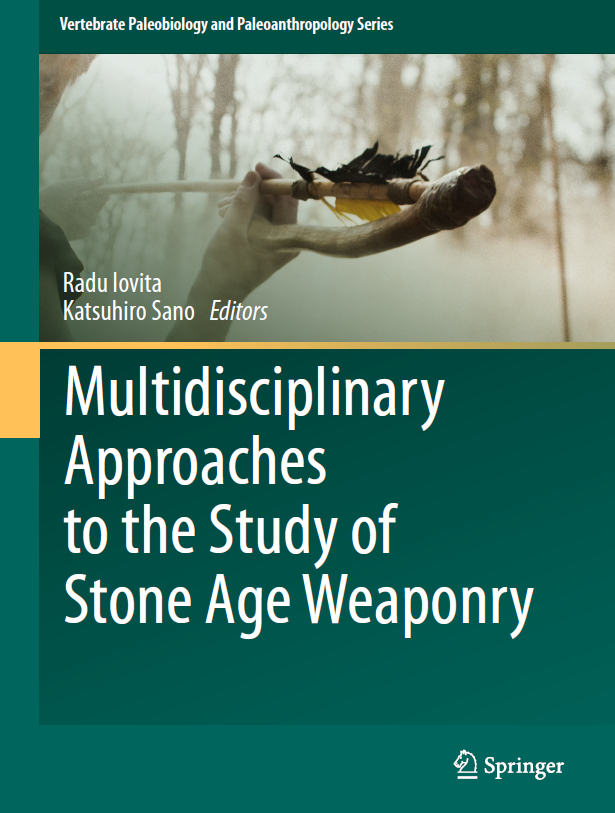弓術の日中交流についてこれから記事を書いていくわけですが、書く前から、自分でも混乱しています。この記事は現状では意味不明な点もあるかもしれませんが、今後、修正して良いものに仕上げていきます。ご理解ください。
一番の問題は和弓も中国の伝統弓道とも、ある程度距離がある立場なので、日中のお互いの気持がよくわからないのです。
中国との交流は4・5世紀頃、応神天皇以降ですが、日本文化への影響は多大。弓についての文献も多く、周礼や後漢書、特に礼記(中国、儒教の経書で五経の一つ)の「射義」の思想は日本の弓に大きく影響し、現在の弓道読本の冒頭にも記されています。日本古代からの弓矢の威徳の思想と、中国の弓矢における「射をもって、君子の争いとなす。」という射礼思想礼から、朝廷行事としての射礼の儀が誕生
全日本弓道連盟 - 弓道の歴史
日本の弓道連盟は、中国との交流は日本の弓道に大きな影響を与えたということをホームページでも認めているのですが、では具体的にどんな交流があり、どのような影響があったのかについては、私が調べた限りでは調査も研究も行われていません1。和弓側は影響は認めるが…以上。という態度のようです。
一方で、中国では伝統弓道が日本の和弓に与えた影響について研究はされていますが、馬明達(国華南師範大学体育学院客員教授、国際武術研究会創立者)によって書かれた論文2では、「錬金術師の徐福が日本に渡ったという伝説を信じるなら、中国の優れた弓術と高度な弩の技術は、秦の時代には早くも日本に渡っていたことになる」と書き、江戸時代に徳川吉宗が中国弓術の観覧を行ったというだけの記述から「清朝初期(17-18世紀)まで中国の弓術が日本に多大な影響を与えた証拠」としているが…。
現在、私に見えている景色は、和弓には中国の影響が大きいと認めつつも深入りしたくない日本側と、伝説まで引用して江戸時代中期まで大きな影響を与えているとする中国側の態度です。どーしましょう。ということで、まずは思想と事実関係の整理から始めます。
最初に中国側で弓についての記録が登場するのは魏志倭人伝ですが、280-297年頃に書かれました。議論があるところではありますが、伝聞とされていて、実際に弓の技術についての交流はなかったと推測できます。
予想される最初の交流は遣隋使(600年~)で、当時の記録に護衛としてアーチャーが船に乗っていたと書かれています。当然、日本の弓矢を所持して状態で中国にたどり着いているので、文書に残らないレベルと、現地において中国と日本のアーチャーで交流の始まりはこれ以降でしょう。
659年、伊吉博徳が唐の皇帝・高宗と謁見を行い、蝦夷の男女2名を献上し、彼らは頭に瓢箪を乗せて、数10メートルの距離から矢を放ち、全矢命中したと記録されています3。このあたりから弓術の交流が記録され始めます。
735年、17年にも及ぶ遣唐留学した吉備真備は帰宅時に大量の弓矢を持ち帰ったことが記録されています4。その後、吉備は軍師・軍事家として大活躍しました。遣隋使・遣唐使で、日本は中国から多くの知識を得たものの、そちらの知識をどう評価するのかという点において、中国で兵法を学んだ吉備が、数々の戦で勝利した史実は、持ち帰った知識の価値を大いに高めたと考えます。

実際の弓術の交流の最古の記録は715年の射礼です。射礼とは483年から宮中で行われていた弓術競技です(*)。そこに日本に派遣された海外の使者(蕃客)が参加する事で日本初の弓術による国際交流が始まります。射礼には自国の弓で参加することになっていました。647年に高麗・新羅(朝鮮)、740年には渤海(中国東北部からロシア沿岸地方にあった)が参加している記録があります。
*日本書紀は正確ではないとされる部分が多いですが、蕃客が実際に来ていたという部分に対する批判はありません。

どのような弓で参加していたのかの記録はありませんが、当時の他の記録を見る限りでは、短いオーバードロータイプのリカーブボウ(角弓)だったと推測されます。この射礼の意義として、大日方は「全官人(日本人)が同じ形状の和弓を所持して射る、蕃客(外国人)はその国の異型の弓で射る。これによって、天皇に対す全官人の服従奉仕と、諸蕃(海外)の従属という天皇を中心とした礼的秩序を表現する儀式となる」としています6。
- 武道全集,弓道講座,現代弓道講座,弓道 : その歴史と技法,弓射の文化史 原始~中世編,を調査しました ↩︎
- Ma, M. (2023). Chinese Archery’s Historical Influence on Japan. In: Chao, H., Ma, L., Kim, L. (eds) Chinese Archery Studies. Martial Studies, vol 1. Springer, Singapore. ↩︎
- 令人戴瓠而立、數十歩射之、無不中者。(唐会要 100巻 蝦夷国), 令人戴瓠立數十歩,射無不中(新唐書 220巻 列伝第145 東夷 – 日本) ↩︎
- 東野治之,遣唐使と正倉院,岩波書店, 2015,P32-33 ↩︎
- 南 秀雄,高句麗古墳壁画の図像構成 : 天井壁画を中心に,1995-03-25 ↩︎
- 大日向克己 [著]『古代国家と年中行事』. https://dl.ndl.go.jp/pid/3103800 (参照 2024-06-22) ↩︎
note : 仁徳天皇十二年(324年)秋七月三日、高麗国が鉄の盾、鉄の的を奉った。との日本書紀の記録は虚偽だとされている